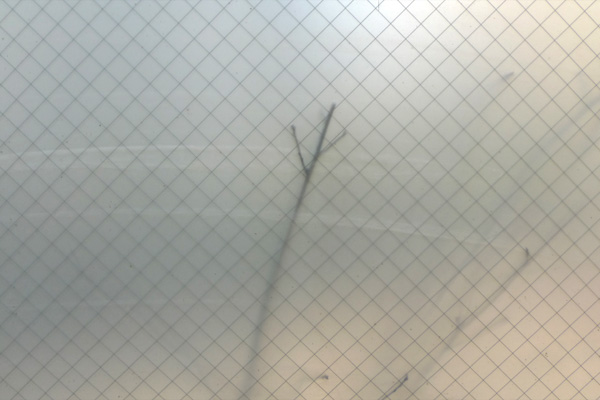(GWも明けましたので、ポチポチと回想的に「直島への旅」を書いていきますよ)
初日は、主に地中美術館と李禹煥美術館(写真上)。地中美術館、やっぱり良い(!)。キレッキレの建築空間、見るというよりも体感的な選りすぐりのアート、そして、それらの関係性… もう、いちいち素晴らしい。僕は結構色々な美術館に行っている方だと思うけれど、やっぱりここが一番かも、と思い知らされる(が、翌日の豊島にて再考させられる・笑)。
そして、李禹煥美術館。写真を見た感じでは、何だかダムっぽいけれど(笑)、中に入るとしっかりと安藤建築。李禹煥(リー・ウーファン)の作品を見るのは初めてだったのだけれど、近代・西洋的コンポジションを東洋的エレメントで作ってみたのかー、とか、緊張感のなかに何か緩さみたいなもの入れることによって作品に寛大さというか大きさ・広がりを与えているのかー(解釈が浅くてすいません…)、という感じに楽しむ。
(美術館に入る前は、柱の広場にある、柱、石、鉄板はそれぞれ独立した作品に見えていたのだけれど、美術館を出る頃には、それらがコンポジションであることが理解できて、うれしかったり)
そして、初日の宿泊先、ベネッセハウスへ(つづく)。

プレGWということで(笑)、直島(と豊島)に行ってきました。6年ぶりの直島、やっぱり素晴らしかったー(!)。詳しくは、またぽちぽちと(仕事せな!)。
(写真はフェリーから撮った海景+浮標)
石山修武,著『生きのびるための建築』、読了。どなたかのツイートを見て、坂口恭平さんによるこの本の書評を知り、読み、とっても面白そうだったので買ってみたのだけれど、結果、とっても面白かったですよ(笑)。
講義をまとめた本、しかも建築系ということで、十数年前に読んだ、安藤忠雄,著『建築を語る』を思い出し、そういえばあの本でバックミンスター・フラーを知り、ハマったんだよなー、とか回想しつつ、この本でもフラーは度々出てきていて、僕が思っていた以上にフラーは建築家のみなさんに影響を与えていたんだなー、直接というより(ある意味)それを乗り越えるという形で、ということも分かったり。
(『生きのびるための…』といえば、ヴィクター・パパネックを連想しがちだけれど、僕が読んだ限りでは関係ないと思われます、多分…。あと、装丁・デザインが服部一成+山下ともこさんなのだけれど、素敵なデザインだし、読みやすいとも思うのだけれど、石山修武さんのイメージとはちょっと違うかなー、と思ったり)